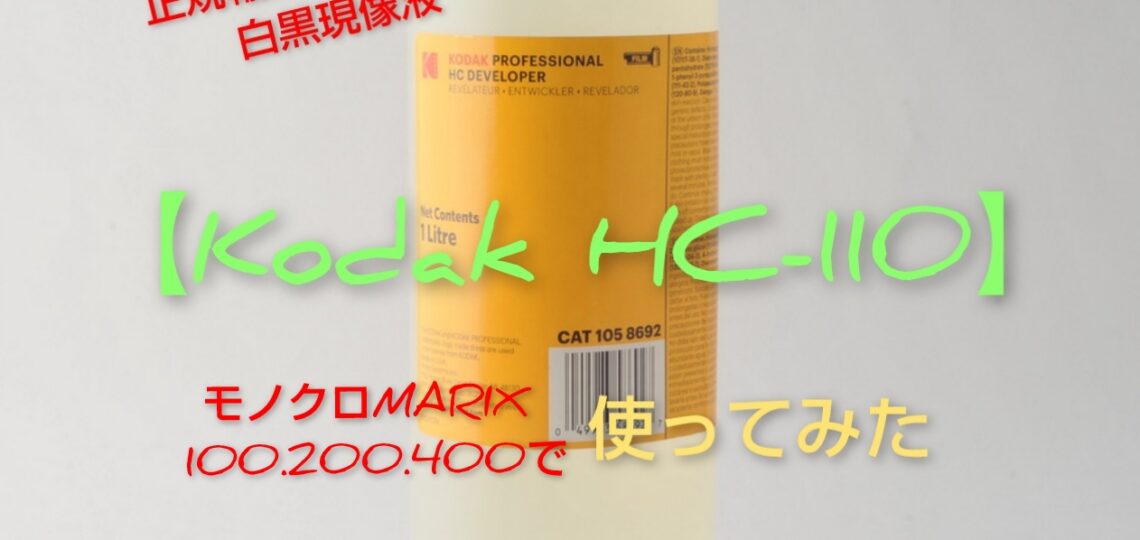Kodak HC-100でモノクロMARIX各種を現像してみた
こんにちは「Kio」です。 さて!今回はモノクロ自家現像民歓喜?!の現像液Kodak HC-100でモノクロMARIX各種を現像してみたのでその作例と現像データ等を書いていこうと思う。 是非最後までご覧ください。 Kodak HC-110ってどんな現像液?? 今回使用したKodak HC-110 コダックが販売している白黒用現像液。 基本1000mlの液体タイプでの販売で、中身はほぼ透明の少し粘度がある液体タイプ。 これは以前はもっとドロッとした黄色味がかった液体だったと思うけど、調べてみた所2019年に現在のタイプに統一されたらしい。 中々に歴史もあり、1962年頃に登場したとされている。 このHC-110だが様々な希釈率で使うことが出来る ※A~Fまでがコダック公式で、それ以外は非公式の希釈率 希釈率 500ml作成時の分量 A希釈(公式) 1+15 31.2+468.8 B希釈(公式) 1+31 15.6+484.4 C希釈(公式) 1+19 25+475 D希釈(公式) 1+39 12.5+487.5 E希釈(公式) 1+47 10.4+489.6 F希釈(公式) 1+79 6.2+493.8 G希釈(非公式) 1+125 4+496 H希釈(非公式) 1+63 7.8+492 その他希釈(非公式) 1+100 5+495 その他希釈(非公式) 1+200 2.5+497.5 基本の希釈率は【B希釈(1+31)】とされていて、G希釈や、1+100、200は主に静止現像用として使われる事が多い。 原液での保存性も良く(旧バージョンではかなり長持ちしたが、新バージョンでは未確認)、とても強い現像力を持ち、やや軟調~標準のコントラストが得られる現像液である。 何はともあれ、次はモノクロMARIX100、200、400をそれぞれ違う希釈で現像してみたデータと作例を見て貰おう。 HC-100×モノクロMARIX100、200、400の作例と現像データ ここからの作例はスキャン後、ライトルームにて、明るさ以外のパラメーターは全て同一での現像処理を行っている。 使用カメラ:OLYMPUS OM-2N 使用レンズ:ZUIKO 35/2&TAMROM 90/2.5(52BB) 使用フィルム:モノクロMARIX100(FOMAPAN100) 現像データ HC-110 1+100 20℃ 60min静止現像(初期30秒のみ攪拌後放置) 使用カメラ:EOS5 QD 使用レンズ:EF28-105/3.5-4.5USM 使用フィルム:モノクロMARIX200(FOMAPAN200) 現像データ HC-110 1+47E希釈 21℃ 5´00(30/60/2) 使用カメラ:マミヤユニバーサルプレス(6×7フィルムバッグ使用) 使用レンズ:Pセコール90/3.5 使用フィルム:モノクロMARIX400(FOMAPAN400) 現像データ HC-110 1+31B希釈 20℃ 7´30(30/60/4) 各現像結果の感想と気を付けたい事 様々な希釈率でHC-110×モノクロMARIX100、200、400の作例と現像データを見て頂いた 感想として それぞれのHC-110希釈×モノクロMARIX100、200、400での個人的な感想はこんな感じ。 まだ結論は出せないが、今回の結果としては一般的な希釈で公開されているデータ通りで100と200は問題なく使え(100は静止現像だけどw)400に関しては現像時間の調整か撮影時の感度を落とす等の工夫は必要だろう。 そして、このHC-110って現像液は様々な希釈があるがゆえに色々試して自分の使い易い、フィルムとの相性が良い希釈率を試す必要があると感じた。 しかし、高希釈で使っていけば実際のコストは結構安くなるので、一見1000mlで高くは見えるが案外コスパも良いのではないかな? 気をつけたい事としては、このHC-110はとても強い現像液と言うことで、基本となるB希釈で使うとフィルムによっては現像時間が5’00を切ってしまう場合も多くある。 現像時間は短いと楽ではあるけど、短すぎると現像結果にバラツキも出やすいので、最低でも5’00は現像時間がある希釈率を選択した方が良いと感じた。 あとは、一度に使う現像液の量が少ないため、細かく量れる注射器タイプや、小さいメスシリンダー等も用意したい。 リンク リンク 最後に MARIXが代理店として発売を開始した【Kodak HC-110】をモノクロMARIX100.200.400 で使ってみた。 使った本数や、希釈率も少なく、まだまだ検証の余地は沢山あるが、概ね100と200 については感度も出てくれそうで、安心して使える感じだ。 しかし400 について … 続きを読む Kodak HC-100でモノクロMARIX各種を現像してみた